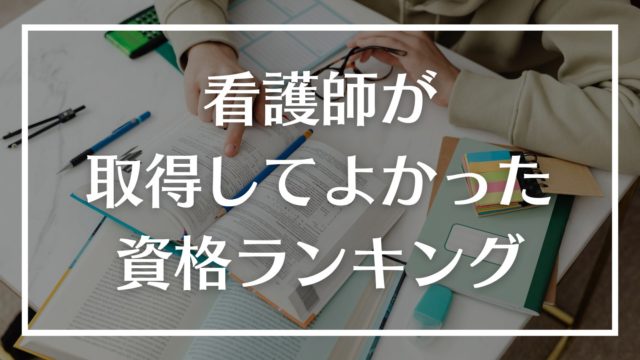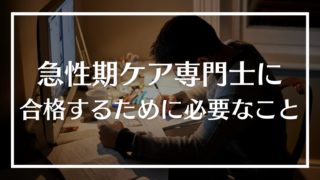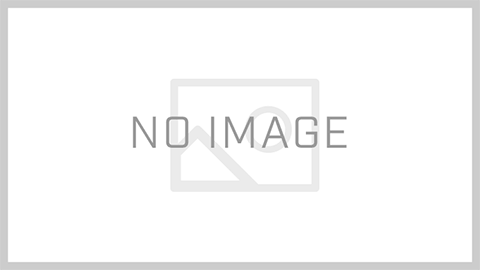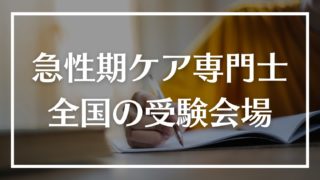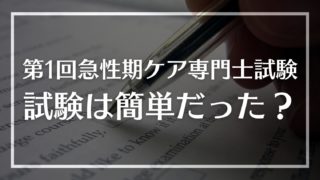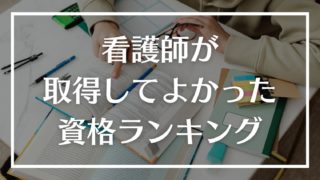
こちらの記事で紹介したJPTECについて詳しく記事にまとめています。
資格取得を検討している方の参考になれば幸いです。
JPTECとは?

Japan Prehospital Trauma Evaluation and Careの略で、Prehospitalつまり外傷現場において迅速かつ適切な観察を行い、Load and Goの適応を判断し、医療機関へ早急に搬送することための方法を学ぶことができるコースになっています。
JPTECでは防ぎうる外傷死(Preventable Trauma Death)の撲滅を目指しており、プログラムの随所でPTDについて触れることになります。
傷病者に接触してから病院に到着するまでのケアなので救急隊向けではありますが、プレホスピタルからインホスピタルへ連続的な処置、観察に繋げるために看護師も理解しておくべきプログラムになっています。
JPTEC資格取得方法

救急隊員や救急専門の医師、看護師向けのJPTECプロバイダーコースについてまとめています。JPTEC協議会公式サイトより一部抜粋しています。
受験資格
・消防吏員
・消防吏員以外の救急救命士
・医師
・歯科医師(救命救急センターまたは救急病院の救急部門に属する者に限る)
・看護師及び准看護師
・診療放射線技師、臨床検査技師及び薬剤師で災害医療派遣業務に従事するもの
・警察官、海上保安官及び陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官で救急業務、救助業務又は災害医療派遣業務に従事するもの
・救急救命士法第34 条第1号から第3号までの規定に基づき救急救命士の受験資格を得ることができる学校若しくは救急救命士養成所、大学医学部又は看護学部及び看護学校(准看護学校を含む)の学生又は生徒で最終学年に属しているもの
受験資格は幅広いですが、医師・看護師以外では災害や救急業務に従事している必要があるので確認が必要です。
コースの内容
①講義(座学)とデモンストレーション
外傷総論、観察処置総論、観察処置各論に分けてJPTECに必要な知識を学びます。
②実技講習
実技では
・観察要領(初期評価〜全身観察〜詳細・継続観察)
・気道管理
・ヘルメット離脱
・頚椎カラーの装着
・ログロール
・(腹臥位からの)体位変換
・バックボード固定
・緊急処置(フレイルチェスト、開放性気胸、腸管脱出、穿通性異物、骨盤骨折、止血)
・車外救出
・シナリオ・ステーション(状況評価から詳細・継続観察まで)
を学びます。
気道管理は看護師でもよく触れる内容なのでギャップを感じずにできますが、その他の実技はほとんどが初めて経験するものになると思います。とても勉強になります。
救急隊がどのように処置をして病院まで搬送しているかがよくわかり、それと同時に救急隊の知識・技術の高さを感じます。
看護師にはあまり聞き馴染みのない言葉が多く飛び交うので、事前にJPTECガイドブックで予習しておくことをおすすめします。予習しておくことで座学だけでなく実技もスムーズに取り組むことができます。

③試験
筆記試験は75%以上の正解が必要になります。JPTECガイドブックやプレテストがあるのでそちらでしっかり勉強して臨みましょう。
実技試験はありませんが、実技達成度評価というものがあります。その日学んだことを確認するものです。救急隊の方々を前に実技をするわけですから緊張はしますが、しっかり勉強していれば問題なく実技を行えると思います。
申し込みに関して
こちらのページから該当する地域の事務担当へ問い合わせする必要があります。
看護師にJPTECをオススメする理由

・救急外来で勤務している、これから配属予定
・Prehospitalの救急隊の活動を知りたい
・外傷患者の対応のレベルアップがしたい
救急外来で勤務していると交通外傷や高所からの転落など外傷の患者さんが多く搬送されてきますが、病院到着までに救急隊が全身観察・評価・処置を行ってきています。
救急外来で患者さんを受ける私たちも、受傷機転や救急隊が観察・評価した内容、また行われた処置について理解することで救急外来での対応もスムーズになりますし、プレホスピタルからインホスピタルへ連続的な処置、観察に繋げることができます。
またABCDの観察方法、ログロールや頚部保護の方法、ネックカラーやバックボードの取り扱いなど臨床でも活かせる内容がたくさんあります。
腸管脱出やフレイルチェスト、刺創の対応なども学ぶことができ、病院外でそのような場面に遭遇したときにも役立ちます。
できれば遭遇したくない場面ですね…!