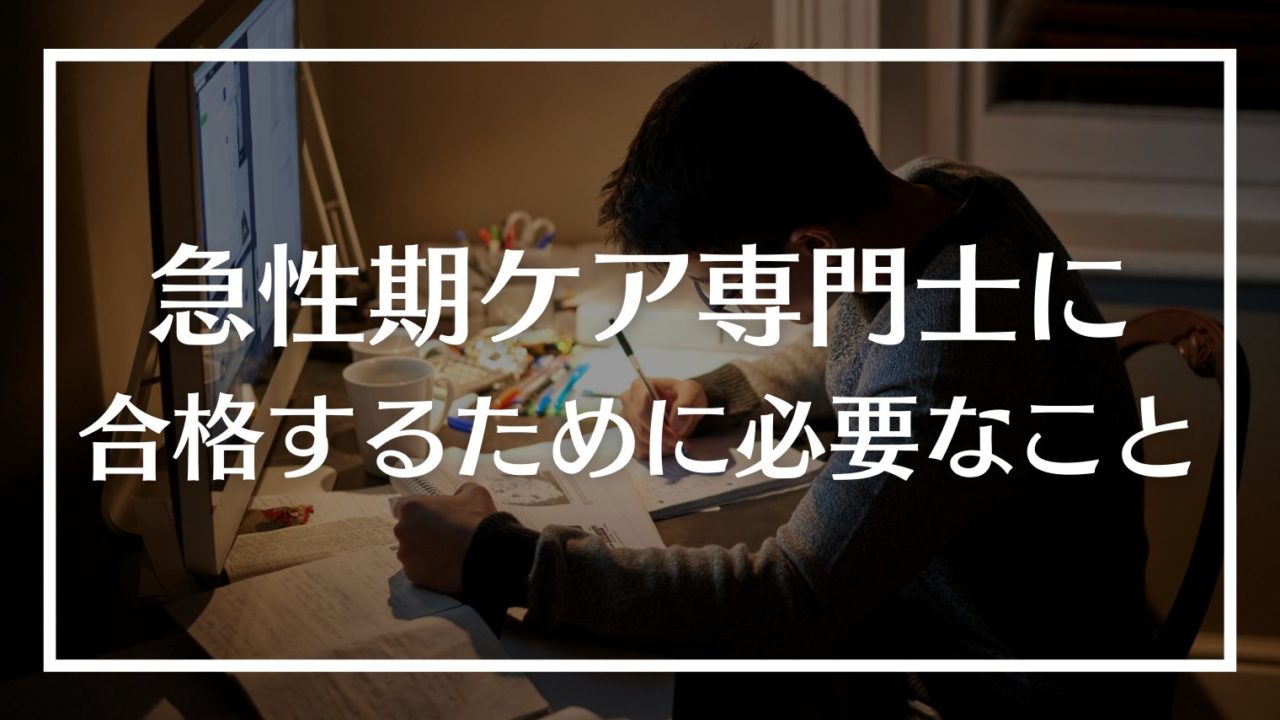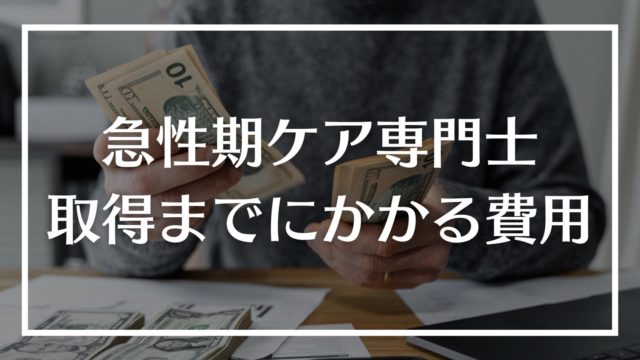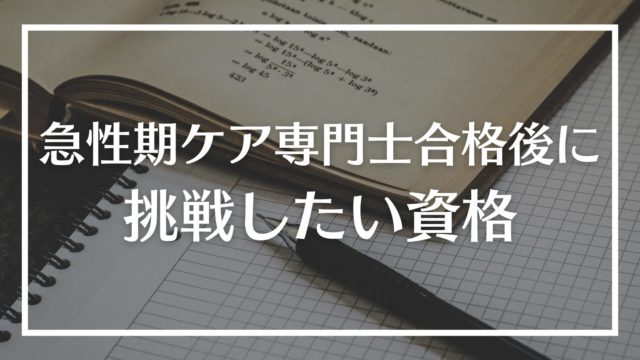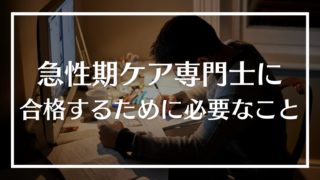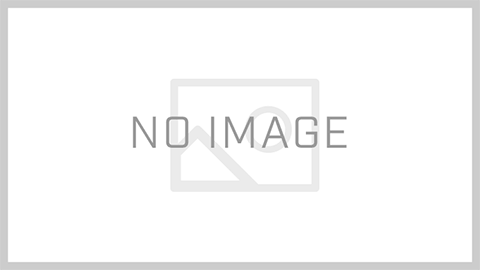2023年5月に新たに開始となる急性期ケア専門士が現在話題になっています。
急性期のプロフェッショナルを目指している方であれば受験を考えている方も多いかと思います。
一回目の試験って不安。
出題内容もわからないし、とりあえず二回目以降に受験しようかな、、
と思った方も多いかと思います。
ですが実は初回の試験だからこそ初回に受験した方が良いことがあります。
今回はそんな不安を解消するための記事をまとめましたのでぜひご覧ください!
試験会場は全国のテストセンターで受験が可能です。
身近な試験会場を探すにはこちら!
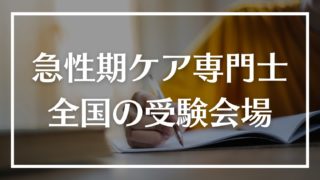
一回目の試験が終了したので下の記事では、実際に試験を受けた方々にInstagramでアンケートを実施し、その結果を記事にまとめてみましたので、ご覧ください!
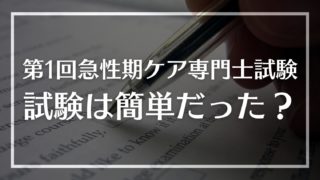
急性期ケア専門士は急性期のスペシャリスト

急性期ケアを学び、シームレスな連携で、命をつなぐ専門士
日本急性期ケア協会ホームページより引用
日本急性期ケア協会が認定している資格です。
シームレス?聞いたことない言葉だけどどういう意味?
シームレスとは“縫い目がない”、“滑らかな”という意味があります。
つまり命のバトンを滑らかに受け取る、受け渡すという意味になります。
急性期ケア専門士は患者さんや施設利用者さんなどを支えるスタッフ(看護師、介護士、リハビリスタッフなど)が、急変時の初期対応、アセスメント、医師への報告を的確に行うスキルを習得できます。
つまり急性期ケア、急変対応におけるスペシャリストといえます!
受験資格
医師・看護師・保健師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士・介護支援専門員・臨床検査技師・救急救命士・放射線技師・介護福祉士
※介護士と介護福祉士の実務経験が合算して3年以上あれば受験可
准看護師
急性期ケア専門士はシームレスな連携を求めているだけあって受験資格も様々です。
2~3年の経験年数があればほとんどの医療従事者は受験可能となっています。
受験までの流れ
-
STEP1申し込み(2023年9月1日~2024年4月10日)1.申し込みフォームから申し込み、受験料の支払い
2.1週間前後で申請書類が届く
3.申請書類に必要事項を記入
4.所定の封筒(クリーム色の封筒)にいれ提出。
締切2024年4月25日必着 -
STEP2審査結果通知が送付される
-
STEP3試験会場の予約全国260か所のテストセンターで受験が可能
-
STEP4試験実施2024年5月10日(金)~5月26日(日)に予約した試験会場にて試験を実施
-
STEP5合否結果の送付2024年7月上旬に合否が送付される
カリキュラム
- 救急医療に関する定義と概念
- 急変発見時の初期対応
- 急性期に求められるリーダーシップ
- 症状別アセスメント
意識障害・呼吸困難・胸痛・腹痛 ・ 吐血・腰背部痛・頭痛・失神・痙攣・めまい・麻痺・発熱 - 急性期医療における家族支援
- 災害時の救急医療
- 超高齢社会における急性期医療
- 小児救急の特徴と課題
- 救急・集中治療部における終末期ケア
- 急性期医療の課題と解決に向けて
試験方法は試験期間内に試験会場でPC入力
日本全国の260か所にテストセンターで実施。
全国どこからでも受験可能なので、出張に行く時間や費用を抑えられるのはありがたいですね!
近くの試験会場についてはこちらの記事にまとめています!
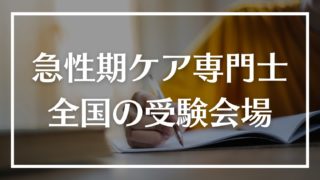
試験期間は2024年5月10日(金)~5月26日(日)に予約した試験会場で実施。
※2023年の試験終了しました。
試験内容は選択式、初回の試験は設定されやすい
試験は5者択一の選択式で行われます。
また出題数は90問でかなりボリュームがある試験内容になりそうです。
また、アステッキの公式サイト、アステッキnewsにて試験対策問題が発表されたのでご紹介します。
問.心電図波形において除細動の適応となるものはどれか。
a.徐脈頻脈症候群
b.無脈性心室頻拍(P-VT)
c.心室細動(VF)
d.心停止(asystole)
e.無脈静電気活動(PEA)
選択肢.
①a.b ②a.e ③b.c ④c.d ⑤d.e
これだけ見ると簡単かもしれませんね!
ちなみに答えは③b.cですね。
急性期ケア専門士は2023年に初めて開始となる資格のため過去のデータなどはありませんが、対象とテキスト、カリキュラムの内容を見る限りでは、救急や急性期に関わる医療従事者であれば合格できる難易度ではないかと思います。
また一般的な試験の特徴からしても、初回の試験は難易度を低めに設定して、次年度以降につなげるため、合格率はか高い傾向にあるようです。
急性期ケア専門士はこんな方にお勧め

急性期・救急で働いている方、働きたい方
今のスキルを活かしてステップアップしたい!!
来年から救急に異動するから今のうちに予習しておきたい!
救急や急性期病院などで働いている方は日ごろから急性期ケアや急変対応に関わることが多いと思います。
普段から関わる事の多い現場だからこそ、エビデンスに沿った正しい知識を持つことが重要です。
また資格を持っているだけで、自分のスキルや経験に箔をつけることができます。
部署の特徴的に急変対応が少なく自信がない
クリニックで働いていて急変対応をほとんどしたことがない。
最近患者さんが急変して何もできなかった、、、
急変対応に興味があっても、部署の特徴として急変に出会う機会が少なく感じている人もいます。
試験を受けることで、急変の経験が少ない方であっても知識を持つことができ、いざ実際に急変にあたった際に自信を持って行動することができ、患者さんの命を助ける手助けができるかもしれません。
地域包括医療に興味がある
将来的に訪問看護で働こうと思っている!
デイケアやデイサービスのスタッフとして地域の施設で働きたい。
現在の医療は入院期間の短縮化、地域医療の発展に向けて地域とのかかわりが重要視されてきています。
急性期ケア専門士は地域と病院の命のバトンタッチをスムーズに行うことで地域包括医療の中心として働くことができます。
訪問看護や地域のデイサービスやデイケアで関わるスタッフにもお勧めの資格といえます。
継続して最新のケアを学習したい
年齢を重ねて、知識が古くなってきた。
色々聞きたいけど、今更こんなこと聞けないよ、、
医療・看護のケアは日々進歩しています。
数年前には当たり前だった知識も今は逆効果なんてこともよくあります。
資格取得後は研修なども豊富にあり、常に最新のケアを学習できる環境ができます。
↓他におススメの資格はこちらの記事をご覧ください。
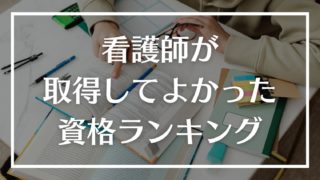
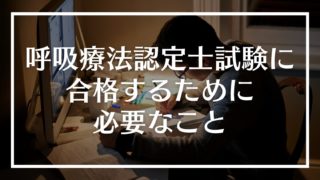
お勧めの勉強方法はテキスト+日々の業務

テキストを熟読
試験が第一回目のため過去問や予想問題が立てにくいですが、テキストには出題範囲が網羅されています。
第一回目の試験であり合格率は高めに設定することが予想されるためテキストを覚えてさえいれば問題ないと思われます!
日々の業務を振り返る
カリキュラムや対策問題を見たらわかるように、急性期ケア専門士の試験はより実践的、実用的な内容が組み込まれている印象です。
普段から急性期や救急に関わる人は、根拠立てて日々の業務に取り掛かるよう意識しているだけでも合格に近づくと思います。
まとめ
急性期ケア専門士の試験は、何度も行われている試験と違って初回のため皆さん不安が多いかと思います。
大まかな流れや試験内容がわかれば少し安心できるかと思い今回の記事を作成しました。
今後も新たな情報が出次第、記事を更新していきますのでよろしくお願いします。