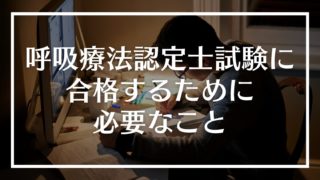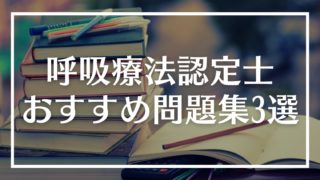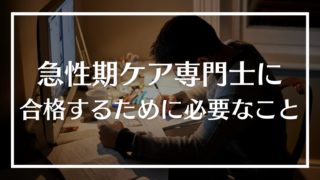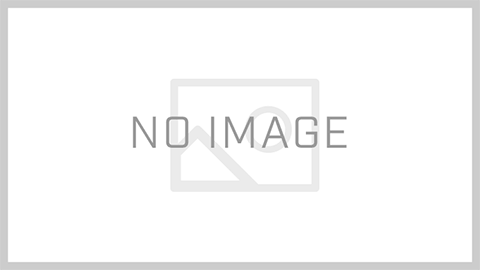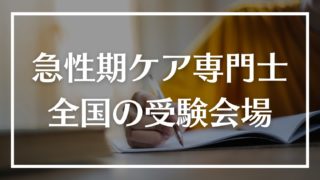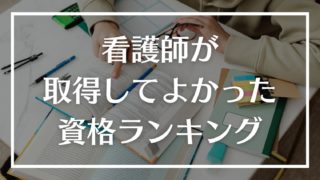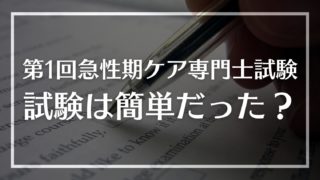目の前の患者さんの呼吸状態が悪いとき、とても焦りますよね・・・
「SPO2の値が低いから酸素を始めないと!」「酸素の量を上げないと!」と考えてしまいますが、アセスメントなしにそのような対応をしてしまうことは大変危険です。
低酸素血症の原因をアセスメントした上で適切な酸素療法を行えるようになっていきましょう。
呼吸不全とは
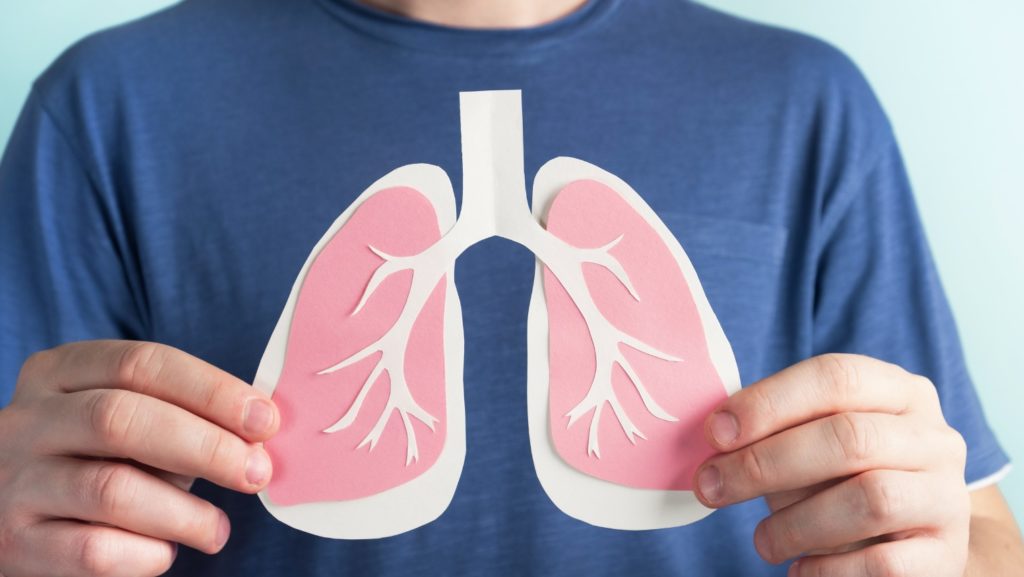
呼吸不全についてはCOPDの記事で触れています。
・Ⅰ型呼吸不全:PaO2<60㎜Hg、PaCO2は正常
・Ⅱ型呼吸不全:PaO2<60㎜Hg、PaCO2≧45㎜Hg
低酸素血症の原因

それでは低酸素血症となる原因について触れていこうと思います。
原因は大きく4つに分けられます。
①拡散障害
②シャント
③換気血流比不均等
④肺胞低換気
①〜③はA-aDO2が開大するⅠ型呼吸不全
④はA-aDO2が開大しないⅡ型呼吸不全
低酸素血症の場合、これらの原因が一つ、もしくは混合して存在します。酸素投与だけしても根本の原因が解消されなければ呼吸状態の改善は期待できません。
①拡散障害
肺胞毛細血管膜が厚くなったり、間質に水分が貯留することでガス交換が障害されている状態です。酸素投与は有効ですが、原疾患への早期の治療介入が必要になります。
拡散障害で問題となるのは酸素です。二酸化炭素は酸素と比較して20倍の拡散能をもっており、二酸化炭素の拡散が障害されることはほとんどありません。つまりⅡ型呼吸不全にはなりません。
原因となる疾患
原因となる疾患:間質性肺炎、肺水腫、放射線肺臓炎、薬剤性肺臓炎、肺血管塞栓症、広範囲な無気肺、COPDなど
②シャント
肺胞内のガスと肺胞毛細血管を流れる血管でのガス交換がないまま、心臓に血液が戻ってしまう状態です。心疾患や肺動静脈奇形などの解剖学的異常でも低酸素血症は起こります。
肺の中のシャント率が50%を超えると、酸素投与してもPaO2の上昇が望めない危険な状態となります。酸素投与しても酸素化の改善に乏しい場合は肺内シャントの存在を考えると良いと思います。
痰貯留が原因であれば吸入や吸引で気道浄化をはかる必要があります。
原因となる疾患
痰貯留による無気肺、肺炎、肺内血管シャント、心内右左シャントなど
③換気血流比不均等
換気量が減少した肺胞に隣接する血管の血流が良くても十分に酸素化することができません。また、換気量が十分な肺胞があっても、隣接する血管の血流が少なくては十分に酸素化することができません。換気と血流のバランスが崩れたために低酸素血症になっている状態です。低酸素血症の原因として特に多いと言われています。
酸素投与は有効ですが、原因疾患への早期治療介入が必要になります。体位変換で酸素化に変化がある場合は換気血流比不均等が存在することが考えられます。
原因となる疾患
喘息、肺炎、肺水腫、慢性閉塞性肺疾患、気管支拡張症など
肺胞換気量の少ない部位に隣接する血管を収縮し血流を少なくすることで換気血流比不均等を是正するシステムです。このシステムが働いて酸素化がなんとか維持されていた場合、血管拡張薬を使用すると酸素化が不安定になることがあります。
④肺胞低換気
肺胞換気量が低下している状態で、体内の酸素量が減少し高二酸化炭素血症となってしまいます。
酸素投与による高二酸化炭素血症の危険性が高いため慎重な酸素投与が必要になります。吸入酸素濃度を調整できる高流量システムを使用して酸素投与する必要があります。
詳細はこの後の酸素療法での項目へ。
原因となる疾患
薬剤による呼吸中枢の抑制、神経筋疾患、慢性肺疾患、肥満、後側弯症など
酸素療法

酸素療法の目的
・低酸素血症・組織低酸素症を改善することで生命維持すること
・呼吸、循環仕事量を軽減すること
血中の酸素濃度が上がっても組織の低酸素が是正されなければ身体は生命を維持することができません。組織へ酸素を届けるHbや心拍出量、血液の状態はどうか。また身体の代謝が亢進して酸素需要の増大に対して供給量が足りているか。などあらゆる情報を評価していく必要があります。
酸素療法の適応
絶対的適応:PaO2≦30㎜Hg
相対的適応:PaO2≦60㎜Hg(SpO2、SaO2≦90%)
血液ガスをすぐに採取・測定できない状況やSPO2モニタがない場合は、呼吸困難感や呼吸促迫、除呼吸、チアノーゼ、冷汗、冷感、頻脈など身体所見から低酸素血症を見抜く必要があります。
看護師の観察する力の見せ所ですね!
酸素投与デバイスの選択
【呼吸状態が安定している場合:低流量システムを使用】
低流量システムとは患者への酸素供給が酸素供給装置より部分的に行われるものです。
デバイス:酸素カニューレ、酸素マスク、リザーバーマスク
低流量システムでは吸入酸素濃度が患者の換気量、呼吸パターン、呼吸回数の影響を受けてしまうため、酸素投与開始時には必ず呼吸状態の評価が必要です。
【呼吸状態が不安定な場合:高流量システムを使用】
高流量システムとは患者への酸素供給が酸素供給装置よりすべて行われるものです。
デバイス:ベンチュリ―マスク、HFNC、インスピロン、アクアサーム
高流量システムでは患者の呼吸状態に影響されず設定した酸素濃度を吸引することができます。
酸素療法の実際
★呼吸状態が安定している患者で酸素療法の適応あり
→低流量システムを使用して低酸素血症の改善をはかる
★呼吸状態が安定しているが、酸素療法の適応があり既往に慢性閉塞性肺疾患がある
→低流量システムで少ない酸素流量から開始するか、ベンチュリ―マスクを使用してCO2貯留に留意しつつ低酸素血症の改善をはかる
★呼吸状態が不安定で酸素療法の適応あり
→高流量システムで低酸素血症の改善をはかる
これらはあくまで一例でしかありませんが、酸素療法は必ず医師の指示の沿って行う必要があります。看護師は医師の指示を確認して、患者の状態をアセスメントし適切な酸素投与方法、酸素流量を選択していく必要があります。
最近ではオキシマスクというCO2の再吸入をしにくい低流量システムが導入されつつあり、私が勤める病院でも使用しています。特に救急外来では既往など十分に把握できていない状態が多いため、酸素投与開始時の第一選択として使用することが多いです。
パルスオキシメーター

★パルスオキシメーターの測定原理
指先に装着したプローブの発光部分から660nm(赤色光)と940nm(赤外光)の2波長の光を組織に当てて、身体を通過してきた光をプローブの受光部で受け、二つの波長における吸光度を測定することで酸素飽和度を測定します。
※パルスオキシメーターは青柳らが1975年に開発!
室内光、体動、循環不全、末梢冷感、不整脈、一酸化炭素、目とヘモグロビン、マニキュアなど
SpO2:90%はPaO2:60㎜Hg程度と言われ、SpO2:90を切ってくると酸素療法の適応になります。しかしSpO2はあくまで飽和度であり100%以上の数値を見ることができません。
漫然と酸素投与を継続すると気づかぬうちにPaO2が200、300とどんどん上昇していき、酸素中毒となってしまう可能性もありますので注意が必要です!
最後に
こちらの記事では呼吸不全と酸素療法についてまとめてますが、試験対策として参考になれば幸いです。